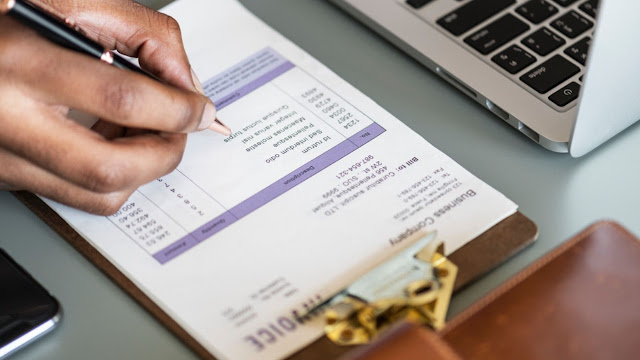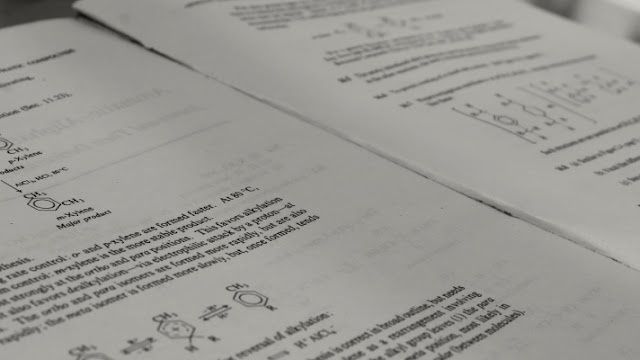その後、ニュースで耳にするようになったのがTPP11。今までのTPPとは何が違うのでしょうか?そして今後の動きはどうなっていくのでしょうか?
TPPとは
TPPとはTrans-Pacific Partnershipの略で、日本語では環太平洋パートナーシップ協定と訳されます。日本語にすると長いのでTPPと短縮形で呼ばれることが多いです。参加国
オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポール、ベトナム、日本、アメリカの合計12か国経緯
元々は2006年に発行されたシンガポール、ブルネイ、チリ、ニュージーランドの4か国EPA(P4協定)でした。この4か国EPAを拡大するにあたり、2009年以降アメリカをはじめとする国々が参加を表明していきました。私たちがよく耳にしている「TPP」と呼ばれるようになったのはこの頃からです。
TPPとはゼロから作り始めた協定ではなく、元々存在していたP4協定の拡大協定だったですね。
アメリカは参加表明する際に、日本も参加するよう呼びかけました。このときのアメリカ大統領はオバマ氏でした。結局、日本が参加を表明したのは2013年のことでした。
その後、交渉は着実に進み、2015年10月に大筋合意に至り、2016年2月4日に署名されました。
日本では2017年1月に国内手続きを完了させており、他の国々の手続き完了を待っている状態でした。
しかし、この流れを止めたのがアメリカ大統領の交代でした。
オバマ大統領とは真逆と言っていいほど、異なった通商政策を掲げていたトランプ氏は、2017年1月に大統領就任するとすぐにTPPからの離脱を発表。
合意されていた内容はアメリカなしでは発行できなかったために、見直しが必要となりました。
TPP11(TPPイレブン)とは
アメリカがTPPから離脱したことで、TPPの内容を見直す必要が生まれました。その際、アメリカが参加していた時の内容と区別するために、TPP11と呼ばれるようになりました。12か国で進めていたTPPからアメリカが抜けたので11ですね。
参加国
オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポール、ベトナム、日本の合計11か国参加11か国の人口は約5億人(世界の約6%)で、GDP合計は日本円にして約1100兆円(世界全体の13%)の規模となりました。
アメリカが抜けてしまった分、かなり小さくなったように感じます。
経緯
2017年1月にアメリカが離脱を表明した後、11か国で新協定「TPP11」の発行を目指すことを決定。2017年11月に大筋合意されました。協定の合意にはかなりの時間が必要となるのが普通ですが、TPPで合意されたものから、アメリカが抜けたところをアレンジするだけでよかったのか、すぐにまとまった印象を受けました。
この合意で新協定の名称をCPTPP(Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership)と呼ぶことが決まりました。日本語では、「包括的及び先進的な環太平洋パートナーシップ協定」と訳されますが、とても長いです。
また、すでにTPP11という名前が定着し始めてしまった今日、CPTPPという名前が広がるかは疑問です。
まとめと今後の動き
今まで、日本がEPAを発行していなかった国は、カナダとニュージーランドです。元々、日本とASEAN間はEPAが結ばれていたので、11か国が参加する協定とはいえ、自由貿易の範囲が広がったとは感じにくいかと思います。
しかし、日ASEAN地域が一丸となった製品がアメリカ大陸の太平洋地域へと関税フリーで出荷できるという利点が生まれました。
反対に、カナダやニュージーランド産の農畜産物が安く輸入できるというのは、消費者目線からすれば利点です。
もちろん、農家をまもるために、数量割り当てやセーフガードが発動するようですが、それでも緩和となるでしょう。
現在、TPP11各国が早期発効を目指して、国内手続きを進めています。
トランプ政権がもうしばらく続く以上、アメリカがTPPに再度参加表明することは当分ありません。メキシコでは7月に大統領選挙がおこなわれ、新大統領が誕生しました。
このように各国それぞれに政権交代のタイミングがあります。
他に離脱を表明する政権がうまれる前に、現在の11か国で発行されるよう期待しています。
2018/12/18追記:2018/12/30輸入申告分より一部の国で適用が始まります!